RFM分析とは?そのメリットと分析方法を解説
ここではマーケティングにおける非常に有名で重要な考え方であるRFM分析について紹介します。マーケティング活動においては、新規顧客の獲得も大事ですが、それと同様に既存顧客の維持管理も大事です。
そして、一口に既存顧客と言ってもその中にはいろいろなタイプの人がいます。タイプとは別に性格分析をしようとしているのではなく、あくまで自社のマーケティング活動においてどのような意味を持っている顧客かを考えるための分析ツールと言っても良いでしょう。
既存顧客をRFM分析によっていわば分類分けすることで、自社にはどんなタイプの顧客が多いかが分かり、またそれぞれのタイプ別にどのようなアプローチをするのが最も効果的かを考えることができるようになります。
RFM分析とは
RFM分析とは、既存顧客をR・F・Mの3つの要素で分類する分析手法です。ここでRとはRecencyの略で、直訳すると新しいこととか最新であることなどといった意味になりますが、RFM分析においては最新購入日、つまり自社の商品を最も直近に購入したのはいつかというその日付を指します。
FとはFrequencyの略で、頻度という意味ですがこれはつまり商品の購入頻度のことです。最後にMはMonetaryの略で、これも直訳すると金銭的なといった意味ですが、ここではいくらお金を使ってくれたかという購入金額のことを指します。顧客を、最新購入日、購入頻度、購入金額の3つの物差しで分類しようとするのがRFM分析だということになります。
RFM分析を行うメリット
RFM分析のメリットですが、比較的簡単な、得ることがさほど難しくない情報を利用して、様々なタイプの顧客を的確に分類できるのが大きなメリットだということができます。
少し考えれば分かるでしょうが、Rが新しく、FもMも大きい優良顧客と、Rが古く、FもMも小さい非優良顧客について、全く同じようなマーケティングアプローチ、例えばダイレクトメールの発送などをしても期待される効果が全く異なるだろうことは想像できるでしょう。
期待される効果やそのためのコストパフォーマンスを考えれば両者は異なるアプローチをして当然ですが、RFM分析により顧客の分類分けがしっかりとできていればこのようなことも十分に可能になるというメリットがあります。
RFM分析のデメリット
RFM分析はある意味で非常に基本的なマーケティング手法であり、デメリットと呼べるものはさほど多くはありませんが、もちろん全くない訳ではありません。
やはり数字を使うものであり、個々の顧客つまり人はなかなか数字だけでは測れない部分が生じる可能性があるということは頭に置いておく必要があります。例を挙げますと、Rが古い人はさほど優良顧客ではないという分類になってしまうでしょうが、それはたまたまであって、もしかすると明日購入しようと考えている最中の顧客かもしれません。
逆にRが新しくても、たまたまその日はライバル店がお休みのためあまり気が進まないながらも自社で購入せざるを得なかっただけの顧客かもしれないというように、一人一人の顧客の真の姿までは捉えきれない可能性があります。
RFM分析の進め方
RFM分析の進め方ですが、データを使うものである以上、まずは必要なデータを集め、それを意味あるやり方で分析しなければなりません。どちらが欠けても的確なRFM分析を行うことはできず、得られた結果もさほど意味を持たないものになってしまうことでしょう。
(1)必要な顧客データを集める
まずは必要な顧客データを集める必要があります。最近はどのデータもデジタル化されていることが多いですから、自社のどんなシステムでどのデータが扱われているかさえ把握できれば比較的簡単に集めることができるでしょう。ただ、注意しなければならないのはあるシステムから例えばRとFを収集し、また別のシステムからMを収集するといったように異なるシステムからデータを集めようとする場合です。この場合、当然のことですが同じ人の同じ期間内のデータを集めるようにする必要があります。人や期間などといった基本的な属性の異なるデータを闇雲に集約しても意味がなく、この後にいくら高度な分析手法を適用したとしても価値ある結果は生まれてきません。
(2)R・F・Mの各指標の基準値を設定する
データを収集しさえすればそれで終わりではなく、R・F・Mの各指標の基準値を設定する必要があります。これは自社の業種、形態、規模などによって異なりますから、自社に合ったものを自分たちで考える必要があります。例えば高級ブランド品を扱うショップの場合、Fとして年1回であっても十分に高い頻度だと言えることもあるでしょう。
一方で日用品を扱うショップの場合、本当に自社を気に入っている顧客であれば毎週購入する人も別に珍しくないかもしれませんし、月1回とかせめて2か月に1回のFでないともう休眠顧客ではないかと考えられるかもしれません。RやMについても同様のことが言え、自社に合った基準値というか分類分けのラインを設ける必要があります。
RFM分析の事例
RFM分析の事例として、ある高級アパレルショップのケースを挙げてみましょう。ここでは年1回以上購入してくれている人を優良と考えて基準値に設定することにしています。
ですからRは別に1年前であっても構わないとしており、Rが例えば昨日の顧客と1年前の顧客とを分けるようなやり方を取り入れていません。他の商品を扱うショップからすればかなり思い切った分類に感じられるかもしれませんが、自社の特徴をよく把握した的確な分類を心がけている訳です。
その一方で、高級ブランドであることを意識しており、年間のMは最低でも5万円ないと優良顧客とは言い難く、それ以下の顧客はRやFの値が良くてもまだまだ自社を特に気に入ってくれている訳ではないと考えて積極的なアプローチをすることにしています。
顧客ランク付け
顧客のランク付けについてですが、顧客に対して適切なアプローチを取る意味でも重要です。ただ、ランク付けのための物差しがただ1つであれば、基準値を1つ設定するだけでそれ以上の顧客とそれ未満の顧客というように2つにランク付けすることができるでしょうが、RFM分析の場合は物差しが3つあれば、各指標に基準値を一つ設定するだけでも2の3乗で合計8つのランク付けが可能です。
もし、各指標について基準値を2つ設定し、良い、普通、悪いというように3つに分類することにすれば、合計では3の3乗で実に27にもランク付けできることになります。これはちょっと多すぎるでしょうから、通常は複数のランクを一まとめにして考えることが適切です。
データ定義
データ定義とはデータ収集に近い意味合いがありますが、収集するよりも前に一体どんなデータが必要なのかを考えることです。分かりやすい事例を挙げれば、ECサイトと実店舗の両方を展開しているようなショップのケースがあるでしょう。
ECサイトだけのデータを集めることにするのか、実店舗だけのデータを集めることにするのか、いや両方とも自社なのだから当然両方のデータをうまく集めることにするのかといったことです。ECサイトで非優良とされた顧客でも、実店舗では優良顧客かもしれません。
ECサイトだけのデータを元にその顧客に対して不適切なアプローチをしては非常にまずいことになる可能性があるというのは分かるでしょう。このようなことを防ぐためにもデータ定義は重要です。
データ収集
データ定義をしっかりと行えば、それを元に必要なデータの収集を行います。複数のシステムで管理されている場合はそれらを集約する必要があるでしょう。また、データ収集とは一度行えば後はもう行う必要がないといったものではありません。言うまでもなくライバル会社やライバル商品の動向、社会情勢などによって顧客の状況は変わります。
自社のマーケティング活動が奏功することによって状況が変わることももちろん期待されます。このような変化についてもしっかりと追えるようにしておかなければタイムリーで的確なマーケティング活動は行えません。繰り返し定期的に行う必要があるということを念頭において効率的な方法を確立しておく必要があるでしょう。
データ統合
データ統合とは、複数のシステムから得られたデータを確実に統合することです。RFM分析に用いるデータは全て各顧客に紐づくものであり、データ統合とは即ち顧客ごとに統合することと言っても良いでしょう。この場合、RFM分析だからと例えば顧客氏名やID番号とR・F・Mの各データさえ統合しておけば十分かというとそんなことはありません。
RFM分析の結果を元にあるランクの顧客に対してはダイレクトメールを送るとか、メールアドレスに電子クーポンを送ることにした場合にそれでははたと困ってしまうのは明らかでしょう。顧客氏名やID番号だけで管理すればそれで良いのではなく、住所、メールアドレス、それに場合によっては電話番号や年齢など、関連するデータも統合しておくことが適切です。
RFM分析まとめ
マーケティング活動において基本的なRFM分析について紹介してきました。企業にとって優良顧客とはどういうものか、それを比較的容易に把握するためにはどうすれば良いかという視点から生まれてきた分析手法です。大事なことは自社のあちこちに分散しているかもしれない顧客データをうまく収集すること、各指標について適切な基準値を設定することです。
また、当然のことですが得られた結果に基づいてそれぞれのランクに分けられた顧客について的確なアプローチをしていく必要もあります。これらにはいわゆる教科書的な手法というものはありますが、やはり自社にとって最も適切な方法は何かということを常に考え、それに合わせてよりよい形に修正していくことも求められるでしょう。


.png)


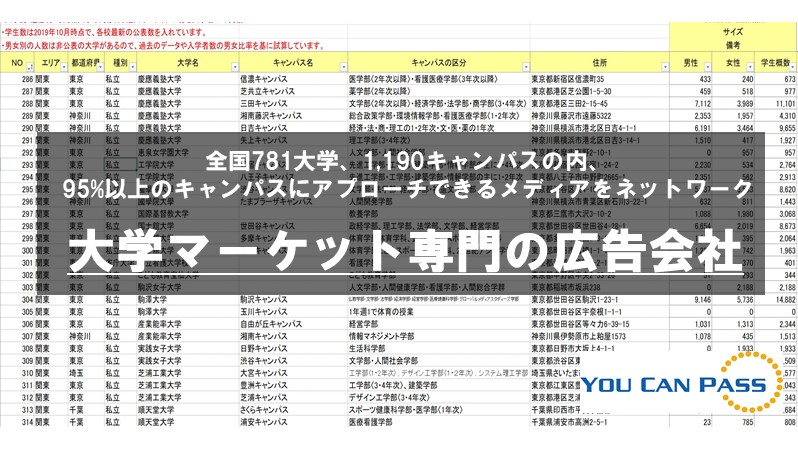
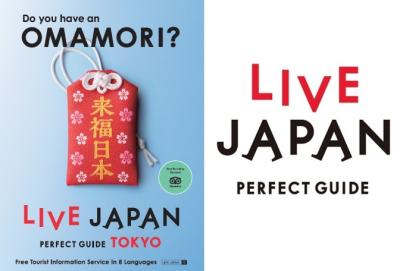





 “御社のサービス・媒体資料を掲載してみませんか?”
“御社のサービス・媒体資料を掲載してみませんか?”